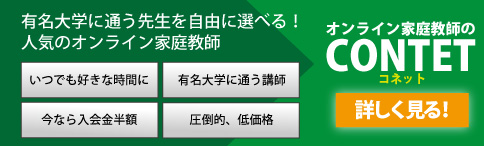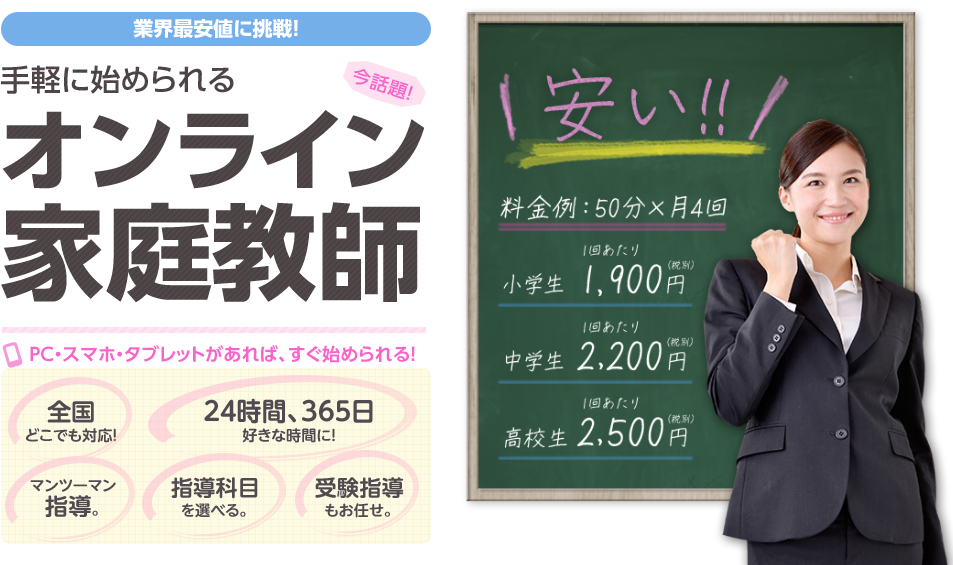受験一辺倒ではなく、本当の意味で人を育てる
学校の先生、塾の講師、またオンライン家庭教師の講師も同じように、教育の場や家庭においても、
教師や親が絶対に言ってはいけないことが一つあります。それは「競争社会」という言葉です。
「勉強しなさい」と激励するのはまだいいとして、その理由として「世の中は競争社会なのだから」「社会に出たら競争なのだから、負けてはいけない」と言うのは、子どものためにならないだけでなく、間違っています。
世の中は断じて競争社会ではないからです。
現代社会に競争の要素がないとは言いません。
サル山のボス争いと同様の現象は確かに起きうる。
しかし、これは社会全体で見れば、ほんのわずかなことにすぎません。
同じ種の内部、人間なら人間社会においては、競争より協力することによって、生き延びるケースの方がずっと多いのです。
競争よりも共存共栄

身近な例を挙げてみましょう。
先ほど話した小学生時代の友人、A君は国会議員を二期務めました(残念ながら落選して現在は国会議員ではありません)。
彼が地元から選挙に出ることになったとき、ぼくは応援に駆けつけました。
選挙運動をそばで見ていて感じたのは、何百人もの後援者が、彼を当選させるために盛り上げていることでした。
作戦が練られると、それに沿って人々が協力し合い、ポスター張りや選挙カーの運転など、まさに一つの目的に向かって疾走していく。
相手陣営にしてもそれは同様です。
最終的には対立候補同士、一対一の戦いになるわけですが、競争と協力を比較して選挙戦全体を眺めると、協力関係の占める割合の方がずっと多い。
それをぼくは「九九%の協力と一%の競争」と呼んでいます。
これはあらゆる世界に当てはまります。
ぼくの好きなヨットレースで、船をスムーズに動かすためには、クルーたちの協力が必要になってきます。
帆を上げ、舵を取り、風向きや天候によってマストを上げたり降ろしたりと、全員が息を合わせ、微妙に動きを変えることで迅速に船を走らせます。
チームワークが乱れると、レースに勝利するどころか、遭難の危険さえ出てきます。
これは日々の学習・生活にも言えることです

実社会においても、競争ではなく、協力が大前提です。
幸いにして『リング』シリーズが世界中で売れましたが、ぼくはだれかと競争したわけではありません。
編集者たちとの協力があって、あのシリーズが生まれたのだし、映画化にあたっては、
監督やプロデューサーをはじめ、もっとたくさんの人たちとの協力関係がありました。
作家としてのぼくの周りには、いろいろな出版関係の人が出入りしていますが、彼らも競争なんかしていません。
むしろ、みんなで順番に、表現は悪いけれどタライ回しのように「あいつのおいしいところを取り合おう」という具合になっています。
どこかの社が抜け駆けしようなんてことは考えられないし、ときにはまったくのライバル社同士が協力し合って本を作ります。
講談社のために書いた原稿を、新潮社の人が沖縄から東京まで運んでくれたこともあります。
講談社が用意してくれた缶詰用のホテルに、毎晩、他社の編集者が集い、飲み食いのツケをすべて講談社にまわしたこともあります。
ある出版社から出た作家の本がベストセラーになったからと言って、他の出版社や作家がそれを叩き落としてベストセラーを送り出すわけではないのです。
社会に出てからは、競争はほとんど行われていません。
むしろ、他人同士がいかによい協力関係を築き上げられるかが大切になっています。
企業内では少人数のグループが協力し合って研究成果を上げ、グループが集まってさらに大きな成功を目指しています。
もちろん、ライバル企業に打ち勝って、自分たちがサクセスを収めなければならない場面もあるでしょうが、そのライバルも内部には膨大な協力関係があります。
学問の世界もしかり。
現在では経済学や物理学、心理学などあらゆる学問がそれぞれの専門分野だけを追究するのではなく、お互いに複雑に絡み合って発展していきます。
もはや研究者一人の能力では立ち向かっていけなくなっているし、他分野の人間が協力しあう方がはるかに得るものは大きいのです。
「生存競争」という言葉はダーウィンの進化論からきていますが、「STRUGGLE FOR EXISTENCE」を「生存競争」と翻訳したのが間違いのもとではなかったかと思っています。
「STRUGGLE」という単語の意味は、「競争」ではなく「あがき」「奮闘努力する」というものです。
本来なら、「生命とは生きるために頑張るものだ」となるべきでしょう。
また、今西錦司さんが説く進化論の基本概念は、「共生」と「棲み分け」であって、競争を否定しています。